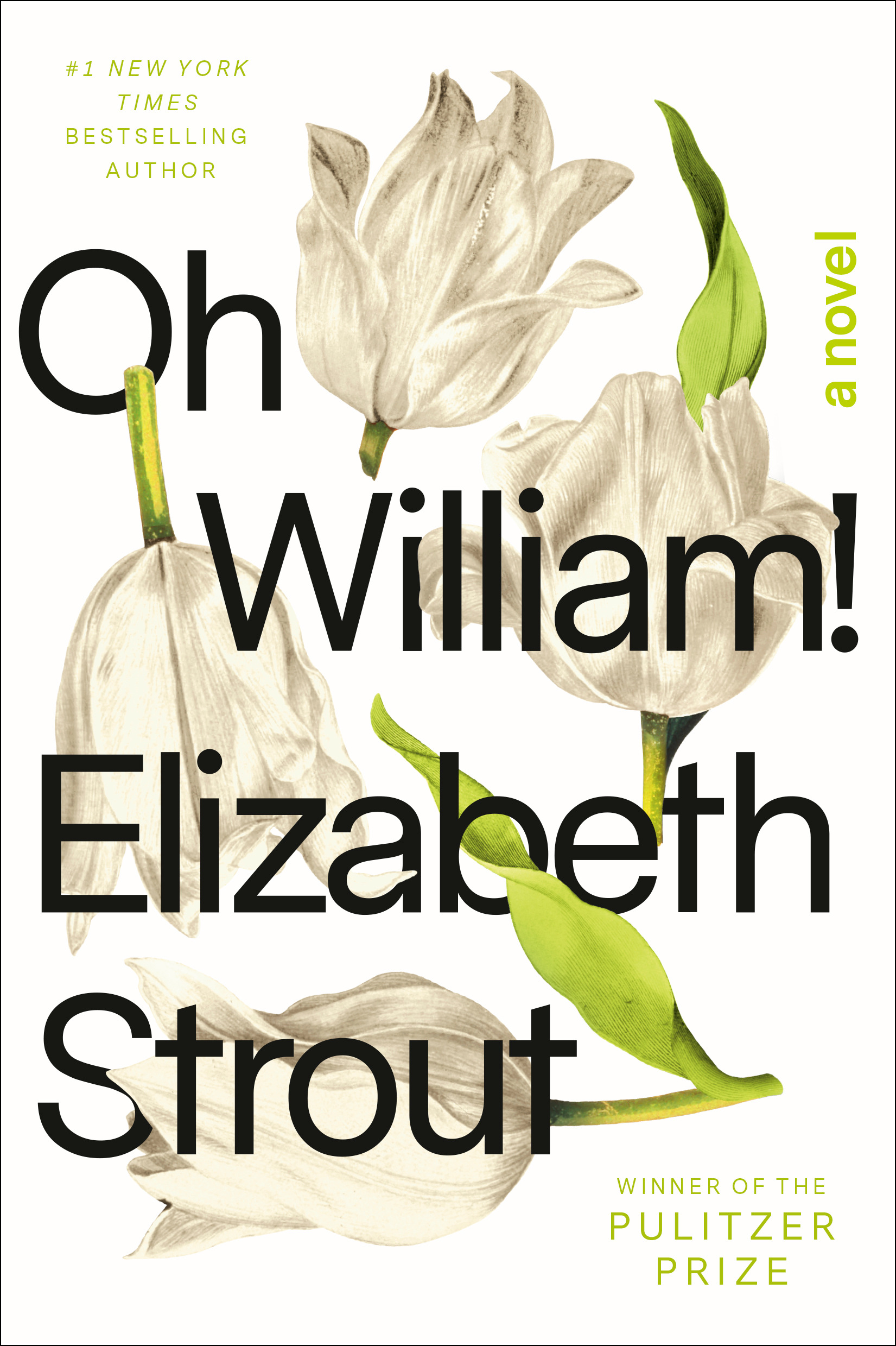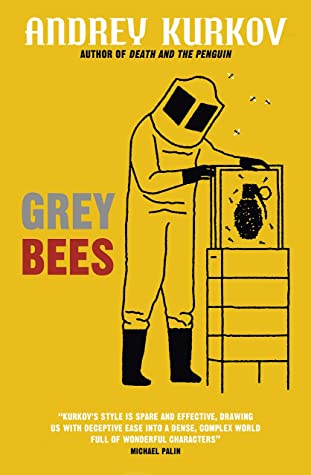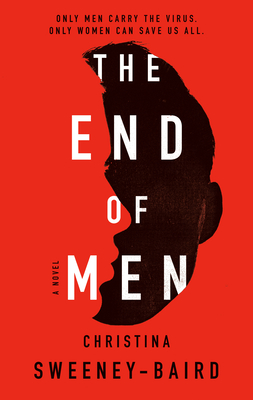Babel, Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution
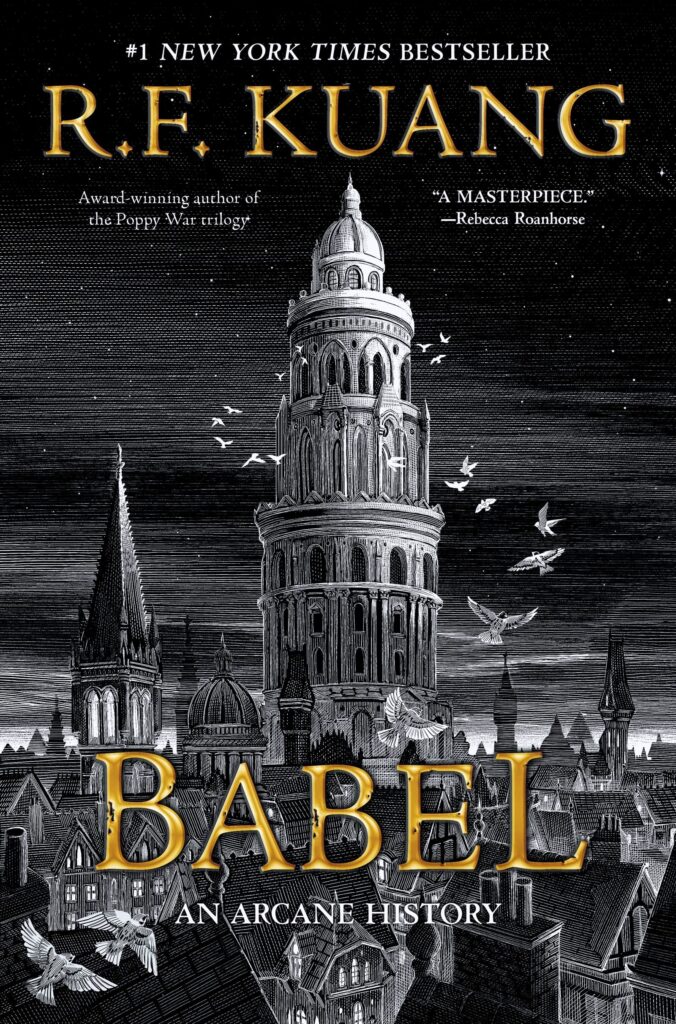
『バベル あるいは暴力の必要性。オックスフォード翻訳者革命の難解な歴史』
“Babel, Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution” by R.F. Kuang, 2022
決定打きた!2022年最高の小説はこれだ!超ド級の言語の力をめぐる幻想ファンタジー。震えた。打ちのめされるようなすごい本だ。★★★★★。
1828年の中国広東、母親をコレラで亡くした少年は、後見者になったオックスフォード大学の言語学教授リチャード・ラヴェルによってイギリスに連れてこられた。少年は教授に英語の名前に改名するように命じられ、ロビン・スイフトと名乗るようになった。ロビンは教授の家でラテン語、古代ギリシア語、英語、中国語の猛特訓を受けてすべての言語に流暢になった。そしてオックスフォード大学の王立言語学研究所”バベル”へ入学した。そこには世界中から多様な言語の研究者が集められ、”シルバーワーキング”という魔術に取り組んでいた。
大英帝国は翻訳の魔法を独占することで産業発展を加速し、植民地支配を拡大していた。銀の棒を内蔵したイギリスの車や船は高性能で、農場や工場の生産性は高く、橋や建築物は堅牢で、武器の威力も強力だった。バベルは政府に銀の棒と、高度な言語能力を持つ人材を供給する国家戦力の機関だった。
シルバーワーキングに通じた言語学者は、銀の棒の両端に2つの言語で同じ意味の言葉を刻む。2つの言語を母語のレベルで扱える者がその言葉を唱えると魔法が発動する。その魔法のパワーは、2つの単語の間に翻訳できない差分があればより強くなる。翻訳で失われる意味の差分が原動力なのだ。2つの言語は違いが大きいほど好ましい。だからバベルには世界中から、西欧言語から遠い言語を母国語とする国々から、多くの若者が集められていた。ロビンは、中国出身のロビン、インド出身のラミー、ハイチ出身のビクトワール、イギリス人の提督の娘レティと親しくなる。
ロビンたちは憧れのイギリスの大学に入学できて喜んだが、やがて不都合な事実に気が付く。彼らが母国語を使って研究に貢献すればするほど、帝国の支配に寄与し、母国を搾取することに気が付いて葛藤する。ロビンは、バベルの打倒を企むレジスタンスのヘルメス・ソサエティの存在を知り、その活動に協力することになった。
バベルの物語は、アヘン戦争の時代の歴史であると同時に現代世界の鏡になっている。エリートによるテクノロジーの独占、文化の盗用によって繁栄する帝国、格差と差別を生みだす社会構造、いま私たちが直面している問題を反映している。ロビンは帝国主義に侵略される母国を救うために立ち上がる。しかしその正義を実現するには、自らを育ててくれた既存の体制に対する暴力と破壊が必要になるのだった。
翻訳を魔法にたとえるこの作品は、外国語の学習者にとって究極の小説でもある。外国語を理解することは、辞書上の意味の対照ができるようになることではない。それはAIでもできる。しかし、翻訳で失われるものを知ること、言語の背景にある文化を理解して言葉を適切に使うことは、人間にしかできない魔法である。言語はコミュニケーションの可能性であると同時に世界を破壊する暴力にもなりうる。言語には翻訳ソフトに任せてはならない領域がある。
英語でこの小説を読みながら、まるで自分が魔法使いになったかのような気持になった。前半は19世紀のオックスフォード大学入学を仮想体験できるハリーポッターのように軽やかな調子だが、後半は魔法が使える人間の倫理と責任を問う重厚な物語になる。控えめに言って大傑作だ。