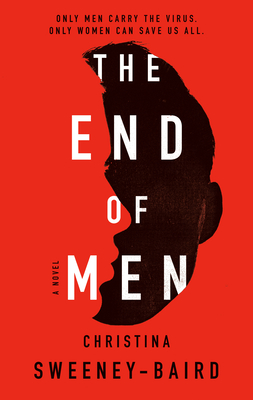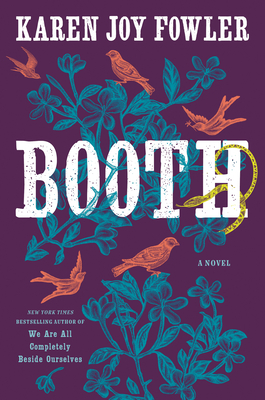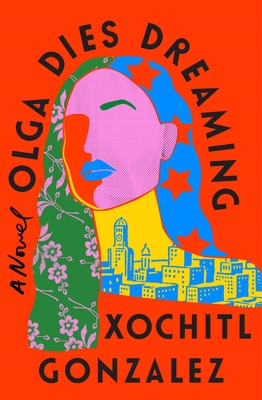The Swimmers
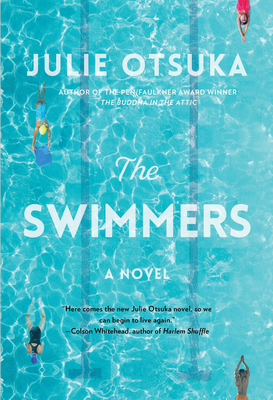
“The Swimmers” by Julie Otsuka, 2022
市民プールで泳ぐ人々は多様だ。朝に速いコースを泳ぐ競泳選手、午後に歩くコースでリハビリをする老人、夕方にゆっくりコースを泳ぐ現役会社員。思い思いに水泳を楽しんでいる。軽く挨拶をするが互いの人生に深くは立ち入らない。程よい距離感覚の地域コミュニティが形成されていた。しかし、ある日、プールの底に謎のひび割れが現れて、日に日に大きくなり、長く続いた平和なコミュニティに危機が訪れる。
文章の魔術師ジュリー・オオツカの本を読むのはこれで3冊目だ。『あのころ、天皇は神だった』『屋根裏の仏さま』と同じで文体がユニークなので10行も読めば彼女の作品だとわかる。
オオツカの文体にはいくつかルールがある。まず登場人物が個人の一人称になることがない。ほぼ三人称代名詞が主語であり一番多いのがweだ。第一章では地元の地下プールで泳ぐ習慣のある住民たちをweと呼び、彼らの集団としての日常を描写する。その中に主人公である初老の女性アリスがいる。
そしてオオツカは特定の登場人物にフォーカスをあてない。アリスは物語を語るうえで便宜上の主人公なのだけれど、本当の主役はアリスを取り巻く家族やコミュニティだ。そしてyouという言葉が出てきたらそれは読者のことであると同時にアリスの娘のことだ。読者は物語の中に強制的に巻き込まれる。
ジュリー・オオツカは同じパターンの繰り返しを多用する。時には1章丸ごと同じパターンが通して使われる。たとえばこの本のある章ではShe remembersが何百回も使われる。自分の名前を憶えているとか、大統領の名前を憶えているとか、延々とアリスの記憶についての説明が続く。ときどきShe does not rememberが混ざる。覚えていることと覚えていないことのリストから、読者はアリスの認知症の進行を知るのだ。
記憶力の減退に悩まされるアリスは、地下プールで泳いでいる時だけは自分を取り戻すことができた。しかし、プールがある理由で閉鎖されてしまうと生きがいがなくなり、急速に衰えていく。思い出すのは戦時中の日系人強制収容所の思い出や疎遠になった娘のことだが、その記憶さえもぼやけていく。
老いと忘却という陰鬱になりがちなテーマを、主観を廃した独特の文体とユーモアで、叙事詩のようなアートにまとめあげた。市民プール、そこで泳ぐ人たち、底のひび割れ、無数のメタファーが散りばめられている。見逃しがないか考えながらもう一度読みたくなる。