The Seven Moons of Maali Almeida
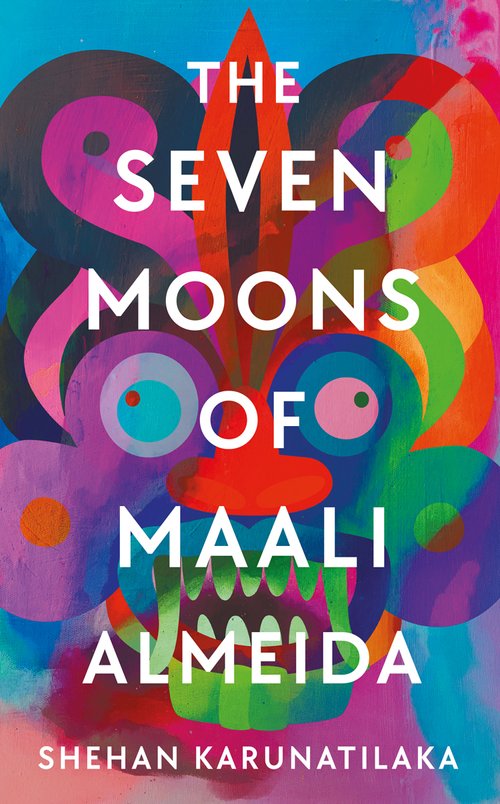
The Seven Moons of Maali Almeida by Shehan Karunatilaka ブッカー賞受賞作。
スリランカの現代政治批評、ヒンズー教の死生観、マジック・リアリズム、知的で冷笑的な語り口…2022年ブッカー賞最終候補に残っているシェハン・カルナティラカは、スリランカ版サルマン・ラシュディだ。
スリランカ人のフォトジャーナリスト、マーリ・アルメイダは目覚めると、異世界にいて意識が朦朧としていた。悪友に飲まされた薬のせいかと思ったが違った。彼は何者かに殺され、煉獄にいるのだった。鬼と幽霊が闊歩する「狭間」で、死者たちは「光の世界」へ入るための事務手続きの行列に並んでいた。死者には煉獄の世界に7つの月(地球の時間で七日間)の期間、滞在が許されている。それは死者が直近の人生を思い出し、忘れるための時間だった。
彼は生前、政府の腐敗を暴くために決定的な写真を撮ってベッドの下に隠していたことを思い出した。その写真を首都のコロンボで公開すれば、政府は崩壊し戦争が終わるはずだった。マーリは七日間のうちに、どうにかして現世に連絡を取り、写真を公開させたかった。同じ家に住んでいた”恋人”のジャキと彼女の従弟のDDが頼みの綱だった。
マーリ、ジャキ、DDのの関係は込み入っていた。DDは家の持ち主であり、タミール人の大臣の息子で、ゲイであるマーリの本当の恋人だった。マーリはゲイであることを隠し、世間体を保つためにジャキとつきあっていたのだ。そしてマーリはDDにもジャキにも内緒で、他の男たちとも寝ていた。
マーリは、自分の写真によって政府打倒を目標にしているが、真人間ではない。ばくち打ちで浮気者の悪い男だ。他の登場人物たちもろくな人間ではない。「善人を探そうとするな、だって誰もいないんだから」「”悪”は恐れるべきものではない。権力を持つものが自分の利益のために行動すること、こそが私たちを震え上がらせるものだ。」「この世界は、善と悪の戦いではない。程度の差こそあれ、邪悪なものの集まりの争いだ」。著者は、腐敗したスリランカ社会の様相を、性悪説の世界設定で表現している。
7日間のマーリの悪戦苦闘も愉快だが、一番引き込まれたのはスリランカ人の考える煉獄と死後の世界観で、日本人の仏教のそれに近いところもあるが、だいぶ違ってもいる。死者は煉獄で直近の人生を忘れてから、次の人生に進む。実は今回のマーリの死は39回目であり、死は特別に意味のあることではないのだ。煉獄を管理しているスタッフも元は人間で神聖な存在ではなく、ただのくたびれた官僚である。道徳的な教えは何もない乾いた世界が滑稽。
スリランカの暗い歴史の風刺作品なので、基本的に語られることは明るくないが、知的でユーモラスな語り口で読者をひきつける。主人公がぶつぶつ一人語りするサルマン・ラシュディの作風に似ている。ただ常に二人称で語る文章が少し読みにくかった。


