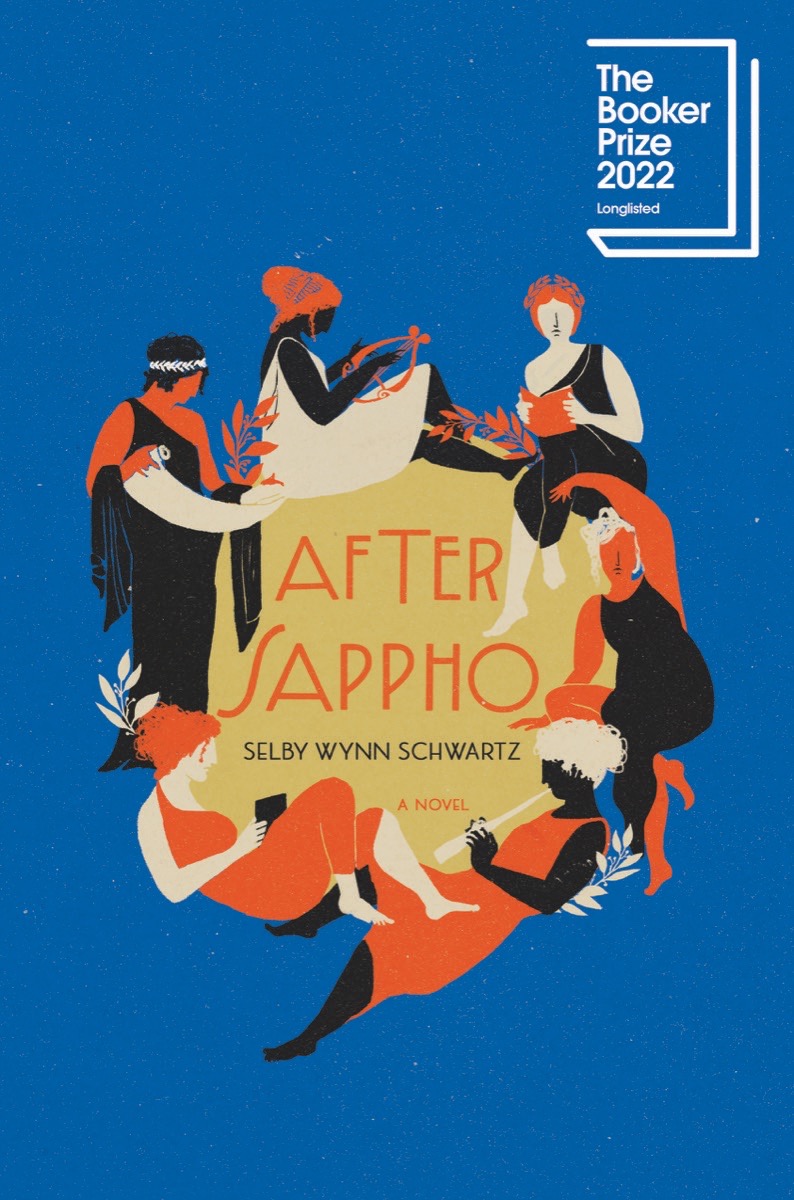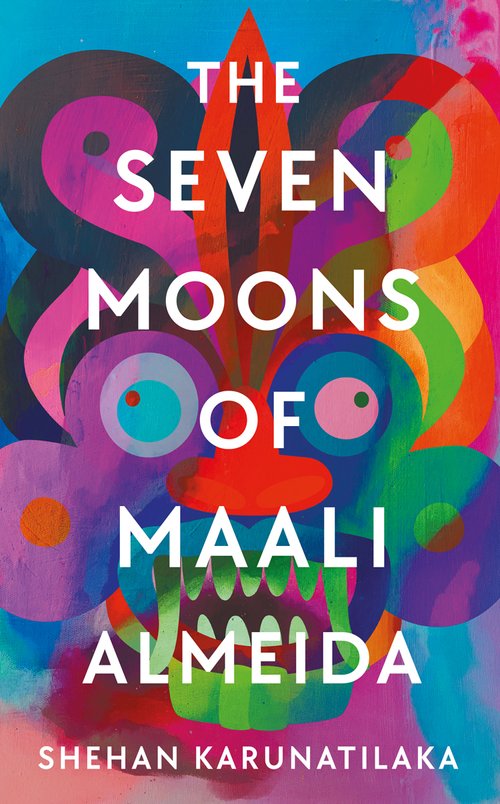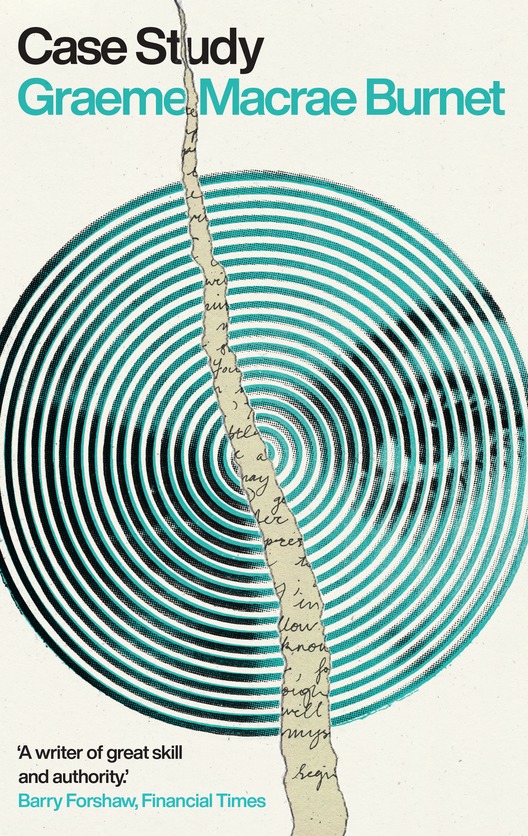The Colony
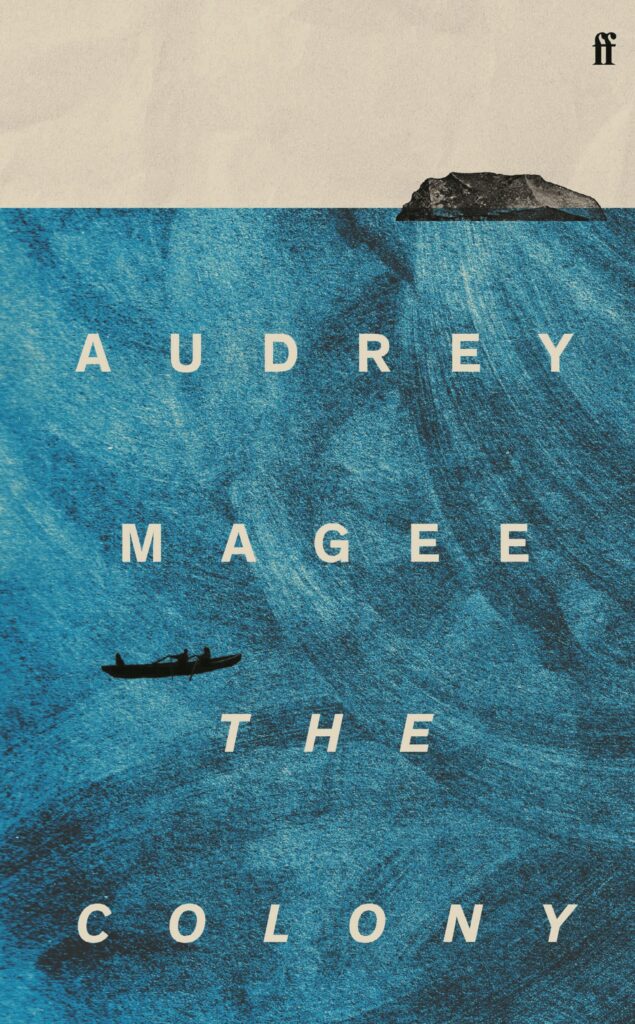
“The Colony” By Audrey Magee, 2022 今年度ブッカー賞ロングリスト作品
1979年の夏、アイルランドの西にある島に、イギリス人の中年の画家ロイドが、島民の案内で船で渡ってくる。彼の絵はロンドンで人気が低迷していた。島の独特の岩礁を描くことで「北半球のゴーギャン」になり、ディーラーの妻を見返してやろうとロイドは画策している。島は過疎化が進んでおり、島民は彼のような外部の人間に家を貸すことで貴重な現金収入を得ていた。
ロイドが到着すると、すぐにもうひとりの訪問者、フランス人の言語学者マソン(通称JP)が島にやってくる。彼は過去5年間、毎年この島を訪問してゲール語の調査を行っている。島民たちは英語ではなく、古い土着の言語を主に使っていた。マソンはこの研究成果で大学教授のポストを確実なものにしようと目論んでいる。
イギリス人のロイドは静かな創作環境を乱すマソンを憎み、フランス人のマソンは英語で島民を汚染するロイドを憎んだ。島の住民には、どちらも島の資源を利用して、一旗揚げてやろうと企む植民者のように見えていた。
島には美貌の未亡人メイリードがいた。夫を船の事故で亡くした彼女は、昼間はロイドのヌードモデルであり、夜はマソンの愛人として暮らしていた。メイリードの義理の兄フランシスは、ロイドとマソンの存在が許せない。大事なものを搾取されていると感じている。
島に住む10代の少年ジェイムズは英語が堪能だった。ロイドから絵を習うようになった。ジェイムズにはロイド以上の天性の才能があったので、すぐにいい絵を描くようになるが、ロイドにアイデアを盗まれてしまう。ジェイムズは文化の盗用だとしてロイドを非難するが、ロイドは互いから学ぶのは当然だとして盗作を認めない。
この小説で語られる植民者と植民地の関係は、単純な侵略と搾取の関係ではない。島の住民も、訪問者も、それぞれの個人的な思惑を持っており、相互を利用しあう複雑な関係が出来上がっている。その関係を続けると結果的に植民地が弱っていく。この島は、世界中にある植民地あるいは植民地的なものを象徴している。
島の物語に、イギリス本土で起きるIRAのテロに関する断章が頻繁に挟まれる。テロのひとつは島のすぐ近くの海上でも起きて、島の中にも不穏な雰囲気が高まっていく。そしてイギリス、アイルランド、フランスを象徴する人物たちの緊張関係がクライマックスに達する。
プロットが秀逸な小説だ。イギリス人の画家とフランス人の言語学者が別の場所でケンカをしていたら、こんなに劇的な物語にならかっただろう。北アイルランド問題の最中の密室のような環境に二人を放り込むことで、人々の心の中の意識的、無意識的な植民地主義を、普遍的な形であぶりだして見せた。
20世紀型の帝国と植民地の関係は消えても、政治的な植民地、経済的な植民地、文化的な植民地の関係は21世紀の世界の至る所にあるということを思い起こさせる問題作。