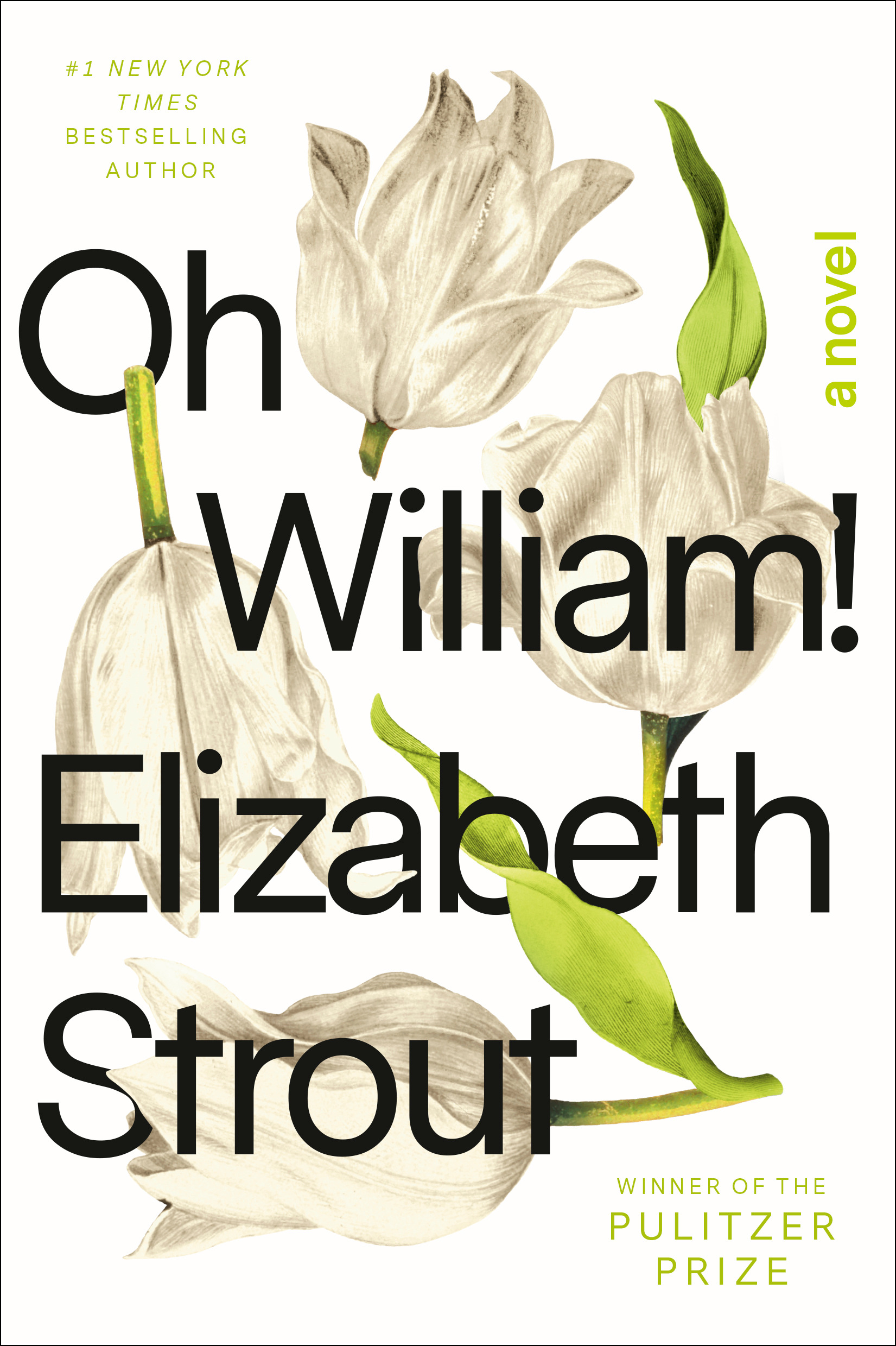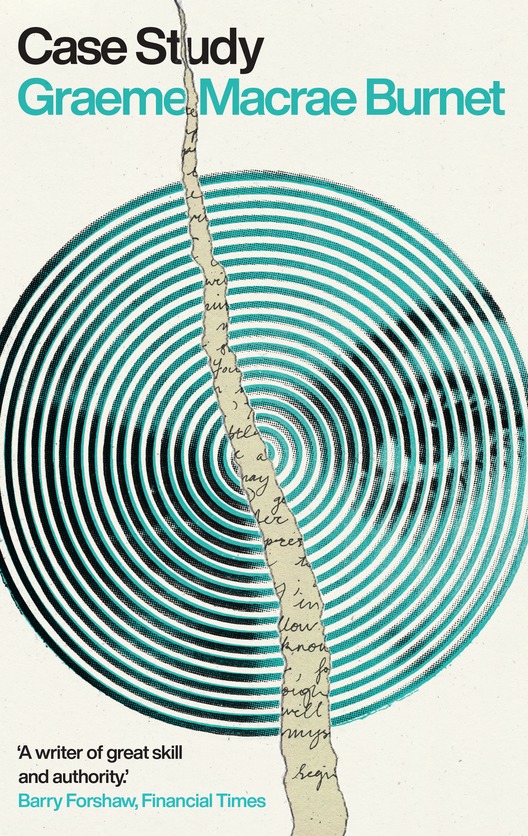The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family
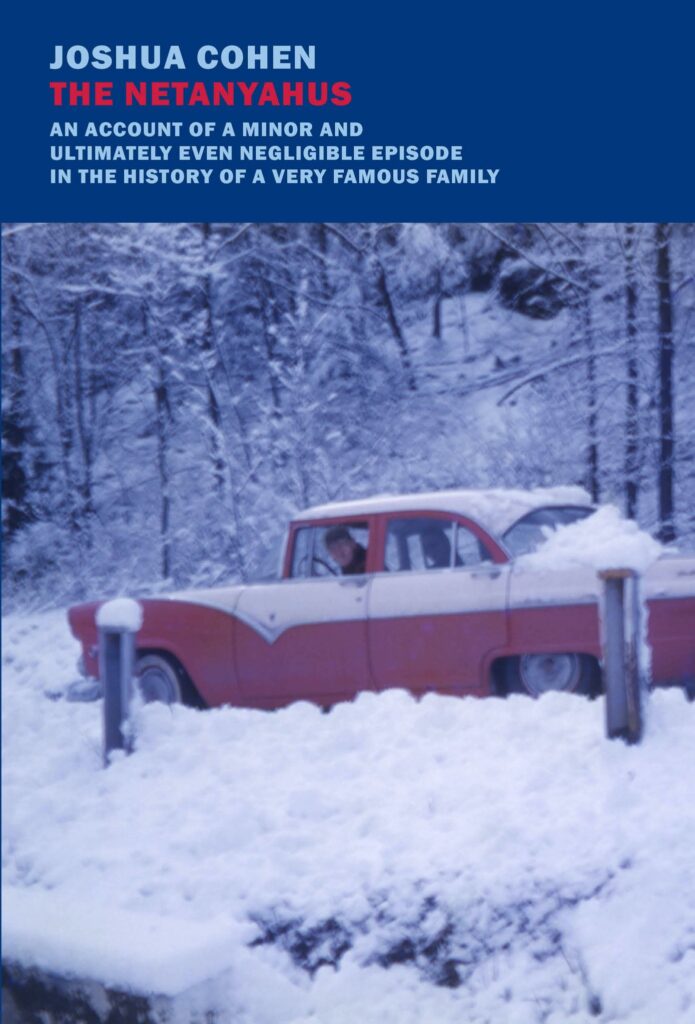
『ネタニヤフ家:ある有名な一族の歴史における些細な、そして最終的には無視できるようなエピソードの記録』”The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family” by Joshua Cohen, 2021 聴いた。ユダヤ感濃縮の暴露コメディ。
2021年度ピュリッツアー賞フィクション部門受賞作。『イスラエルの王』と呼ばれ、長く同国の顔として君臨したが、2021年に汚職で王座から引きずり降ろされたベンヤミン・ネタニヤフ元首相。彼の父親ベン=シオン・ネタニヤフは歴史学者で一時期アメリカのコーネル大学で教授を務めた。このときベンヤミンを含むネタニヤフ一家はアメリカで生活をしていた。
この作品の主人公は1950年代の後半、ニューヨーク州郊外にある大学の教授で税制史を専門にするルーベン・ブルーム。「私はユダヤ人の歴史家だが、ユダヤ人の歴史を研究する歴史家ではない」を口癖にしている。ルーベンはユダヤ人ではあるものの、自分はブロンクス育ちのアメリカ人だというアイデンティティを持っている。
ルーベンは上司に呼ばれる。近く新しい教授を雇うので採用委員会のメンバーになってほしいという依頼だった。採用候補者というのがイベリア半島中世史を研究するベン=シオン・ネタニヤフだった。最新の論文は15世紀にユダヤ人を大量にキリスト教に改宗させたスペイン異端審問に関するものだった。ブルームはユダヤ系という理由で、このテーマを的確に評価できると上司から見込まれたのだった。専門ではないのに。
ネタニヤフの論文を読みながらルーベンは自分のユダヤ人ルーツを強く意識せざるをえない。ネタニヤフの論文はユダヤ人はいくら他の宗教や文化に同化しても、呪われた宿命から逃れることはできないと示唆しており、ルーツから離れたいルーベンは暗澹とした気持ちになる。
ネタニヤフが大学の採用面接に訪れることが小説の冒頭で予告されるが、実際にやってくるのは最後の部分だ。それまではルーベンが経験するユダヤ系アメリカ人の滑稽で憂鬱な体験や、保守的な両親との面倒なつきあい、そこから起きる事件がユーモラスに語られる。タイトルのネタニヤフが登場するまで前置きがとても長い本だ。
訪問日になってみると予想に反してベン=シオン・ネタニヤフは一人ではなく家族全員を引き連れてルーベンの家にやってくる。そこには子供時代のベンヤミンも含まれる。ベン=シオンは傲慢で厚かましい男で、一緒についてきた妻や子供たちも問題児ばかりでルーベンは頭を抱えてしまう。ルーベンにとってネタニヤフ家はユダヤ人のルーツを象徴する存在なのでなおさら気持ちが落ち込むのだ。
どんな文化も濃縮すると独特の臭みが出てくる。ユダヤ人の知的さ、抜け目のなさ、被害者意識、権利意識、家族主義…ジョシュア・コーエンはユダヤ文化をココトコと煮詰めていって、出汁がよく効いたスープを作った。首相一族の大変不名誉な暴露もあり。うへえと笑える民族の悲喜劇。ピュリッツアー賞のフィクション部門賞を受賞。